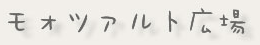モーツァルト一考・代表 加藤明のコラム(K618)
《アイネ・クライネ・ホロニガ・ムジーク》
聴いて欲しいモーツァルト その16
K618 加藤 明 その日「ライオン」は梅雨の重苦しさをひきずった曇天と小雨模様を連続的に繰り返しておりました。
名曲喫茶「ライオン」、渋谷道玄坂に昭和元年創業という老舗中の老舗である。
自由ヶ丘の新聞配達員であった私が正体不明の先輩マツダさんからこの「ライオン」の存在をおしえてもらい、朝刊配達後日課のように通うようになったのはようやく都会の空気に慣れはじめた5月初旬でした。
初めて訪れた「ライオン」はそれまで見たこともない音響装置とレコードの多さ、整然と音響に向かって並べられたテーブルと椅子、天井が高く2階建てというスケールの大きさ、そして暗めで優しく包み込む照明や古い調度品、さらには清楚で気品のあるウエィトレス(ああ、どうしてクラシック喫茶の女性はみんな近寄りがたい気品を漂わせるのだろう!)、それらが醸し出す静謐な空間などで一瞬のうちに18歳の私を虜にしたのです。
当時の私の神様はバルトークとストラヴィンスキーという20世紀音楽の旗手でした。
学校で習うように、バロックから古典派へ、そしてロマン派から20世紀音楽へ、という具合に系統立てて聴いてきた訳でもないのに、私の音楽史の果てしない旅はこの二人に出会ったところで長い逗留を強いられておりました。
たぶん、この世にこの二人の音楽しかいない、というほどの傾聴ぶりだったと想います。
そんな訳で、「ライオン」では《弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽》や《春の祭典》などをリクエストしては全身でまさに体感しておりました。
その日の午後、ストラヴィンスキー自らが指揮した《春の祭典》をリクエストし、聴き終えて夕刊の配達時刻までに帰ろうとしましたが生憎の雨がまだ降っておりました。
しかたなく、傘のない私はしばらく出入口で雨の止むのをじっと待っておりました。
その時、一人の背の高い男が突然、たどたどしく私に声をかけてきたのです。
その青年は以前にも「ライオン」にいるところを見ていたせいか、はじめて会ったという感覚ではありませんでした。
「・・渋谷の駅まで行きますが・・もしよかったら一緒しますか?・・」。
彼は傘をもっていたのです(!)。
そこでなんの躊躇もせずその好意に甘える私。
「・・ええ・・すみません・・」
お互いの顔も満足に確認しないまま、二人は雨のなか道玄坂から渋谷までの10分余を連れ立って歩くことになりました。
どうしたものか、歩き始めてすぐに私は彼に異様な孤独の臭いを嗅ぎとりました。
支えるもののない孤独、いや、支えられることを拒否している孤独さみたいなものです。
でも、直感的に、なんか馬が合う奴だ、と感じました。
私たちはスタスタと駅に向かって歩きはじめましたが、その間のほとんど独り言のような対話の相手がその後今日まで私に傘を差し出す奇特な男になろうとは、まったくもって予想もしておりませんでした。
その青年、ササキ。
滋賀は彦根出身のササキは当時20歳のウルドゥー語を学ぶ外語大の学生でした。
私は立て続けに、一方的に喋ったと思います。
とにかく話し相手に飢えていましたから。
ハンガリーの民族音楽を普遍的なところに昇華したバルトーク、その繊細で生命力あふれる音楽がいかに私を刺激し啓発的であるか、ストラヴィンスキーの《春の祭典》のリズムがどれだけ鋭利に世界の不安を表現したものであるか、先日東京文化会館で初演されたペンデレツキの「広島の鎮魂曲」を聴きにいった時の印象から、音楽という芸術がいかに直接的に時代の空気を反映する能力特性をもっているか、などを私は熱く語ったように記憶しています。
考えてみると奇妙なことなのですが、渋谷までの10分間はお互いの音楽についての意見交換にとどまらず、それまで縁もゆかりもない二人がお互いの出自についても触れるほど濃密な出会いの時間となったのでした (いや、音楽と「ライオン」とコーヒーがつくった縁とゆかりであった、というべきなのかもしれませんが)。
- ◇
それからというもの、私は井の頭線沿いのササキのアパートに入り浸るようになりました。
それまでの「ライオン」に出向く時間が彼のアパートに変換されたようでもありました。
私に傘を差し出したササキは新聞販売所のマツダ兄同様、今まで会ったこともない特異な感受性をもった驚くべき個性でした。
その芸術全般に対する関心の広さと深さ、語学力と表現力、読書の質と量、絵の創作力、そして知識を吸収するスピードの速さ、これらは彼の跳びぬけた感性と知的能力の高さを雄弁に語っておりました。
徹底して知ることに貪欲なのです。
他人が知っていることが知らないということはストレスなのです。
しかし、安易に訊かないし、おもねることは嫌いなのです。
結局、自分というものがわからないのだ。
自分がわからない自分のことを受け容れ、わかろうともがいているだけなのです。
彼は本さえ預けていればいいような、純粋に孤独を楽しむところがありました。
その一種のつましさは呆れるほど一貫したものでした。
朝と夜は自炊するストイックな生活スタイルは至って自然であり、悠然とすらしていました。
新聞販売所の自分の部屋は一畳もない狭いものでしたから、ササキの部屋の八畳間は大変広い贅沢な空間でした。
しかも、多くの本棚の脇に置かれていた石膏でつくられたヴィーナス風のトルソーが、この部屋の気分を収斂しているかのように映り、一層贅沢な雰囲気をつくっていました。
私が割り込んで邪魔になるような他の付き合いもなかったようなので、自立できない新聞配達員は図々しく彼の知的で質素で広いアパートを訪れては、堰を切ったように己を語り、語っては彼の反応を期待するのでした。
当時、劇団「民芸」が東横劇場で日本初演となるサルトルの「汚れた手」を公演したばかりで、全身の感覚を研ぎ澄まして観た私はそのことも泡を飛ばして喋ったものです。
実際、待ちに待ったサルトルの戯曲であり、宇野重吉や滝沢修を目の前で観ることができた喜びは大きく、とりわけ主役の滝沢修の演技には圧倒されましたから。
そんな観劇談を得意気に話す私に、サルトルの「存在と無」の原書をさりげなく本棚からとりだしてみせた時のササキに私は腰を抜かしたものでした。
フランス文学に傾倒していた彼から私はいろんな作家や作品を紹介してもらいました。
ガスカル、ビュトール、サロート、ソレルス、クレジオなどのフランスの作家やジョイス、
ウルフなどの英語作家、「ブリキの太鼓」のグラスなど、彼の口からは多くの作家や作品が吐き出されては私を惹きつけていくのでした。
調子にのって、「嘔吐」の原書を手にフランス語を教えてもらおうと試みましたが、私のセンスと基礎力ではそんな荒行に耐えられなかったのはいうまでもありません。
また、彼はゴダール、トリュフォーのヌーヴォーロマンや当時一世を風靡したパゾリーニなどの映画に私を誘っては、私とは全く異なった視点からの鋭利な感想を語っていたものです。
忘れていましたが、当時は一連の学生運動が世間を騒がせておりました。
私には何のことかわかりませんでしたが、彼も少しは闘争のイデオロギ−に共鳴した活動をしていたようにも思います。
- ◇
さて、こんな具合に、ササキとの濃密な関わりをもってしばらくすると、私のなかに変化が生じてきました。
ササキとの知の探検的な日々の楽しさとは裏腹に、新聞配達員としての毎日が序々に疎ましいものに感じられるようになったのです。
元来飽きっぽい性格の私は、(新聞配達を通しての)リアルな目標をもっていなかったこともあって、彼のアパートに寝泊りするようになり、年末のある日、ついにはアルバイトを無断で放棄してしまったのです。
新聞販売所の親父さんや世話をしてくれた仲間に顔向けできない自分、無分別で無責任極まりない自分、つまり、フリーター落第の図であり、釣り糸のない浮きが東京という大海のなかにポカンと浮遊した、それは瞬間でもありました。
それからというもの、私は自分の身勝手さから起こした過ちに気づきつつも、謝罪もせずに現状の打開策を必死に考えることになりました。
これから私はどうやって暮らしていけばよいのか・・・・・。
いったい、この東京でなにができるのだろう・・・・。
なかなか答えがでません。
長い間、この不毛とも思える自問に苦しみました。
なにしろ、謝罪のために戻ることすらできない、駄目な自分への問いかけでしたから。
そうして、ササキとの濃密な時間を担保してくれた新聞配達のアルバイトを自ら意識的に拒んでしまった、という己の不甲斐なさに改めて思いが至ったときに、私は彼にうめくように言いました。
「ササキ・・よう・・おれ、やっぱり実家に戻ることにする・・・」と。
その時の彼のなんとも寂しそうな表情を私は正視できませんでした。
「・・帰らなくても、いいんじゃない・・・」
なんども、彼は言いました。
「・・いや、・・東京はおれの住むところではなさそうだから・・・」
なんべんも、私は応えました。
自分自身に言い聞かせるように、です。
こうして、間もなく生活の基盤をなくしたフリーター落伍者と孤独な美学の徒の別れの日がやってきました。
故郷の秋田になにがあるのか、といっても、確固たるものはもちろんありません。
その自信のなさからくる揺らぎのなかで、重いからだをひきずるように、田舎に帰るべく上野駅までやって来ました、もちろんササキも一緒です。
上野に着いてから、列車の出発時刻まで少し間があり、駅前の喧騒を二人で歩きました。
短い期間ではあったが共に過ごした濃密で劇的な時間を懐かしむように。
偶然とはいえ、「ライオン」からはじまったそれはわずか半年に満たない形而上のドラマであり、二度と再び上演できない特別な舞台であったことをお互いに了解していたようでした。
出発時刻が近づいたころ、ササキは何を思ったか、不意にその辺のお土産屋に入りました。
そして、貴婦人がチェロを弾いている陶器のオルゴールをひょいと買い求めました。
「・・・これ、持っていって・・」
さりげなく、どこまでもさりげなく、下を向いて手渡すシャイな男です。
「・・・サンキュー、悪いな・・・」
箱の裏書をみて、このオルゴール曲が《アイネ・クライネ・ナハトムジーク》であることを知ったのはその時でした。
どうして、モーツァルトなんだ?と思いながらも箱を開けるのを楽しみにしておりました。
いよいよ秋田行きの列車がホームに入ってきました。
ササキは乗り込んだ私の後ろについて車内に入ってきました。
ホームでは居場所がなかったからに違いありません。
出発ぎりぎりまで傍から離れません(そうだ、彼は一緒に秋田に行きたいのだ!)。
言葉が要りませんでした、というより、言葉がみつかりませんでした。
やがて重い沈黙を切り裂くように、「この列車は間もなく出発です、お見送りの方はホームに・・・」という素っ頓狂で鼻にかかったアナウンスが車内に流れました。
「・・・・・・・・・・・・」、それまでとは違った緊張感が私を襲いました。
「・・じゃ・元気で・・・・」、とササキ。
眼は相変わらず下を向いていたと推います。
彼の顔を正視できない私。
「・・うん・・おまえさんも・・」。
このあわいは私の青春を象徴するものとなりました。
彼はそのまま、(握手もせずに)二度とこちらを振り返ることなく、ホームの雑踏の中に消えて行きました。
(「ああ、あっけなくササキが行ってしまった、俺はいま秋田に向かっている」)
列車が突然ガタガタン!、と鋼鉄のうねりを発したあと、重々しく動きだしました。
その瞬間、例えようのない寂寥感とともに、何かが確実に私の胸からこぼれ落ちました。
そして、代わりになにか温かいものが私の深いところに宿されたのを意識しました。
こぼれ落ちたものが何で、その宿されたものとは何であったか。
もしかして、それは、私の中からスッパリと東京が抜け落ちたということであり、あれから40年経った今でも、変わることなく保たれている距離感が示す、奇妙な友の刻印が宿された、ということかもしれません。
どうして彼があの時《アイネ・クライネ・ナハトムジーク》をプレゼントとして選んだのかは今もって不明です。
ひょっとしたら、私に適いそうな曲が他になかっただけかもしれません。
ただ、あのとき列車で聴いたこのオルゴールの音色が、それまで聴いたどんな《アイネ・クライネ》よりも寂しげでほろ苦いものであったことだけは忘れることができないのです。
(了)
- 「ライオン」は昭和20年、戦災で焼失するも5年後に建て替えて再開しほぼ60年、現在もその当時のままで迎えてくれる。
- この《アイネ・クライネ・ナハトムジーク》はあまりにも多くの名演があり、今回は私の好みから一枚のみ紹介したい。
【推薦曲と推薦盤】
○指揮 シャンドル・ヴェーグ
演奏 ザルツブルク・モーツァルテウム・カメラータ・アカデミカ
- 録音 1986年10月
- APRICCIO COCO−80239
- このシャンドル・ヴェーグとモーツァルテウム・カメラータの組み合わせによるモーツァルトのセレナードとディヴェルティメント全集(10枚組・25曲)も同じレーベルで出版されています。
一生の友の感のある素敵な企画で、是非お薦めします。
- ある弔辞・・・聴いて欲しいモーツァルト その15
- モーツァルトの先生を追いかけて・・・聴いて欲しいモーツァルト その14
- 鳥肌がたった“秀麗無比なる”協演”・・・聴いて欲しいモーツァルト その13
- 兄を送った「白鳥の歌」 ・・・聴いて欲しいモーツァルト その12
- 下宿屋「鎌田」と17歳のモーツァルト ・・・聴いて欲しいモーツァルト その11
- ススムさんへのレクィエム ・・・聴いて欲しいモーツァルト その10
- やってみたかった「音楽授業」・・・聴いて欲しいモーツァルト その9
- 加藤くん ホラッ リンツだよ・・・聴いて欲しいモーツァルト その8
- パパゲーノに託されたモーツァルトのメッセージ・・・聴いて欲しいモーツァルト その7
- 「夕べの想い」に想いを馳せて・・・・・聴いて欲しいモーツァルト その6
- 「小林秀雄を撃った短調の弓」‥‥‥聴いて欲しいモーツァルト その4
- 「好漢 関清和に贈る言葉」‥‥‥聴いて欲しいモーツァルト その3
- 「モーツァルトのサヨナラ音楽」‥‥‥聴いて欲しいモーツァルト その2
- 「ミサ曲 ハ短調」に込められたもの‥‥‥聴いて欲しいモーツァルト その1
- ジュノムがザルツブルグに 、久元祐子が秋田に!
- K304 特別な響きのソナタ
- 会報「モォツアルト広場」創刊によせて